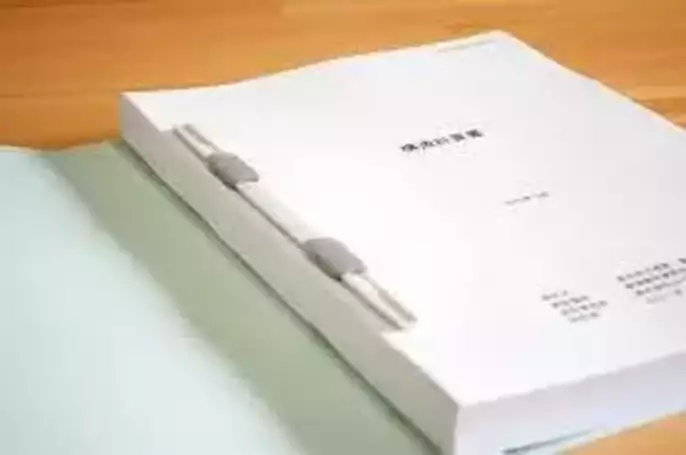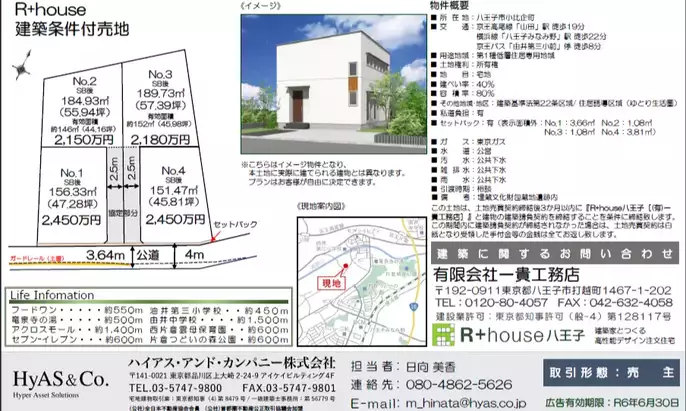こんにちは!皆さん、突然ですが構造塾の佐藤さんのYouTubeをご覧になったことがございますか。木造住宅の構造計算、構造設計の最新情報や技術を分かりやすく紹介しているチャンネルですが、動画配信以降、動画のコメント欄を通じて、家づくりを検討されている全国のエンドユーザーから「自分の地域に優良工務店があれば教えてほしい」という声が多く届いたそうです。このことを受け、株式会社M's 構造設計は、【全国の良質な住宅の作り手リスト】を企画され、その第一弾が少し前に発表になりました。
第一弾には残念ながら間に合わなかったのですが、、第二弾の募集を知り弊社も応募した次第です。そんなことをきっかけに、今日は耐震性能について記事を書いてみたいと思います。家づくりを進めるうえで重要な「耐震性」。そしてその指標でもあり、近年よく見聞きする「耐震等級」という言葉。地震に強い家にしたいという要望は当たり前になっており、どのように、どのくらい、地震に強い家にしたいのか、よく理解をして自分で判断することが大事ですね。
耐震等級とは
建物の強さ・強度の指針で、品確法(ひんかくほう 住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって定められている住宅性能表示です。現在、耐震等級は3つの段階が設けられています。ベースとなるのが耐震等級1です。
「耐震等級1」
数百年に一度発生する地震の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震の地震力に対して損傷しない程度。(建築基準法同等)
「耐震等級2」
等級1で想定される1.25倍の地震が起きても倒壊・崩壊しない
「耐震等級3」
等級1で想定される1.5倍の地震が起きても倒壊・崩壊しない
万全ではなかった耐震性
2016年4月に起きた熊本地震は、震度7の地震が立て続けに発生するという、観測史上初めての災害となりました。
現行の建築基準法の規定に沿って建てられた住宅でさえ、倒壊および全壊の被害を受けました。
建築基準法の耐震基準が大きく見直された昭和56年以降の住宅は、阪神淡路大震災および東日本大震災でも、ほとんど倒壊被害は見られていません。このことからも、熊本地震による被害の衝撃が窺えると思います。これまでも大きな地震の度に見直されてきた住宅の耐震性について、再び議論が始まっています。
現行の建築基準法の規定に沿って建てられた住宅でさえ、倒壊および全壊の被害を受けました。
建築基準法の耐震基準が大きく見直された昭和56年以降の住宅は、阪神淡路大震災および東日本大震災でも、ほとんど倒壊被害は見られていません。このことからも、熊本地震による被害の衝撃が窺えると思います。これまでも大きな地震の度に見直されてきた住宅の耐震性について、再び議論が始まっています。
耐震等級3=地震に強い家?
最高等級である耐震等級3の建物なら地震に強くて安心!そう思ってしまうかもしれませんが、結論から言いますと決してそうではありません。地震に強い家 ≠ 耐震等級3 なのです。重要なのは、しっかりと構造計算をしているかどうか です。そして構造計算には種類があり、やり方によって耐震性に差が生まれること知っておくことが大事です。ここが「しっかりとした」構造計算であるかどうかに関わってきます。
わかりにくい構造計算の違い
壁量計算
筋違などの耐力壁を立面図と平面図、屋根の重さを基に配置する方法で、木造2階建てまでで一般的に使われる簡易計算の方法です。耐力壁の配置までは指示が無く、かつ骨組みを考慮しないため信頼性の低い計算となります。
許容応力度計算
筋違などの耐力壁の他に柱の位置や梁の大きさ、荷重のかかり方、建物のゆがみ、バランス、上下階の直下率などを考慮して計算します。その為、立面図と平面図の他に矩計図・構造図(柱・梁の骨組み)・基礎伏せ図・仕様書(屋根材・外壁材等)・地盤調査報告書が必要になり、時間も費用もかかりますが、信頼できる計算となります。「しっかりとした構造計算」をしているかどうかが重要です、と前述しましたが、の「しっかりとした」は、つまり「許容応力度計算」のことです。
耐震等級3≠許容応力度計算
建築確認や品確法の申請上、構造計算の種類は問いません。耐震等級を取得していることと、複雑な許容応力度計算を実施していることは、必ずしもイコールではありません。壁量計算でも耐震等級3は取得できます。耐震等級3という同じ等級の中でも、壁量計算と許容応力度計算による差が生まれるのです。「耐震等級3を標準仕様にしています。」「耐震等級3の家です。」このような売り言葉に惑わされないよう注意が必要です!重要なのは「許容応力度計算」を実施しているかどうかです。地震に強くするために壁の量を増やせばいい、というわけではありません。壁のバランスがとても重要です。一定方向のみの揺れには強く、別方向の揺れには弱いという構造になりかねないからです。木造2階建ての一戸建ては、構造計算をしなくても法律上問題なく建築することができます。つまり、木造2階建ての場合、構造計算の種類はどちら?という話以前に、そもそも構造計算をしているのか、いないのか、この判断・確認をする必要があります。
判断するのは施主となるあなた自身
家づくりにおいて、地震に強い家にするために、どのような方法でどこまで強くするのか、判断できるようにする必要があります。壁の量を増やしたり、地震に対抗する強い壁(耐力壁)をたくさん配置すれば、その分地震に強い家にすることは可能になります。ですが、その分コストがかかったり、広い空間に壁が出現したり、窓が小さくなったり、間取り上の制約や費用面にも影響が及びます。2016年に発生した熊本地震は、震度7の余震、同じく震度7の本震、大地震が2回連続で発生しました。2回目の本震で、多くの建物が倒壊してしまいました。その中には耐震等級3の家も含まれています。また首都圏直下型の地震発生確率は70%とも言われています。これらを踏まえ、これからの家づくりにおいて、何度もお伝えしているように「地震に強くする」ことは絶対条件です。そしてその強さは、大地震が連続して起きたとしても、逃げる時間を確保するだけでなく、その後も安心して暮らすことができる、法律で定められている性能以上の性能・強さなのではないでしょうか。大地震が起きた時、家が丈夫で倒壊しなければ、自宅で待機するという選択をすることができます。自宅がシェルターとなってくれるのです。